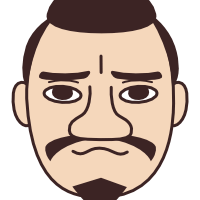龍造寺隆信
1529.3.24 〜 1584.5.4

龍造寺隆信(胤信、隆胤)は、現在の佐賀県にあたる肥前国の武将・大名です。下剋上で少弐氏から独立して肥前国で台頭すると、大友氏の版図を奪って北九州に一大勢力を築きます。恵まれた体格と凶暴さから、肥前の熊と呼ばれました。南九州を制した島津氏と争い、沖田畷の戦いに敗れて討死しました。享年56。
- 龍造寺隆信の武将タイプ
- 侵略
龍造寺隆信は何をした人?このページは、龍造寺隆信のハイライトになった出来事をなるべく正しく、独特の表現で紹介しています。きっと龍造寺隆信が好きになる「肥前の熊と恐れられ大躍進したが哀れな最後を遂げた」ハナシをお楽しみください。
- 名 前:龍造寺胤信 → 龍造寺隆胤 → 龍造寺隆信
- 幼 名:長法師丸
- あだ名:肥前の熊、五州二島の太守
- 戦 績:51戦 37勝 12敗 2分
- 出身地:肥前国(佐賀県)
- 領 地:筑前国、筑後国、豊前国、肥前国、対馬国、壱岐国、肥後国
- 居 城:水ヶ江城 → 村中城 → 須古城
- 正 室:龍造寺家門の娘
- 子ども:4男 3女
- 跡継ぎ:龍造寺政家
- 父と母:龍造寺周家 / 慶誾尼
- 大 名:龍造寺氏20代当主
肥前の熊と恐れられ大躍進したが哀れな最後を遂げた
龍造寺隆信は、一介の国人であった龍造寺氏を大友氏、島津氏に次ぐ戦国大名に押し上げ「肥前の熊」の異名をとりますが、大名なのに討ち取られてしまったことで有名です。
いくつかの肖像画が残っていますが、でーんと太った様子が描かれている点が共通しており、掛け軸のフレームになんとか収まっている感じが熊っぽさを助長しています。
見た目が熊っぽいだけでなく、熊さんもびっくりする非情さと腕力で龍造寺隆信は九州第三の勢力に成り上がりました。
というのも、龍造寺隆信の父と祖父は騙し討ちによって殺されたため、多感な青年だった彼は他人を信じることができず、冷酷な復讐の権化となったのです。
もともと持ち合わせていた暴力性のリミッターが外れた龍造寺隆信は、主家を滅ぼし、同盟相手を踏み台にしてのし上がっていきます。
/
主従も恩義も
関係ねえ
\
1545年、龍造寺氏は少弐氏に従っていましたが、父と祖父を討ったのは少弐氏の家臣・馬場頼周でした。その翌年、曽祖父と一緒に挙兵した龍造寺隆信は馬場頼周を討ちます。
執拗なまでに少弐氏を痛めつけ、1559年に少弐冬尚を自害させて滅ぼし、少弐氏の家臣たちをやっつけて回りました。
父の主君である少弐氏を討つという下剋上を果たした背景には、父と祖父を亡くした龍造寺隆信を保護してくれた蒲池鑑盛の協力がありました。
しかし、肥前の熊にはそんなの関係ねえ。
大恩ある蒲池鑑連の死後、その子である蒲池鎮漣を家来にしますが、裏切りの気配をちょっと感じただけで一族もろともぶっ殺してしまいました。
大友宗麟との関係においても、従っているように見せておきながら、1578年の耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗すると、手のひらを返したように大友領を奪って勢力を拡大しました。
/
痛恨の判断ミス
沖田畷の戦いで惨敗
\
暴力と恫喝によって急速に勢力を拡大した龍造寺隆信は、同じくハイペースで九州制覇をねらう島津氏と対決することになります。
きっかけとなったのは、有馬晴信の裏切りでした。龍造寺隆信はこれを許さず、討伐に向かいますが、有馬の援軍として現れたのが島津家久でした。
島津本隊ではなく島津家久だけなら楽勝と考えた龍造寺隆信は、6千ほどの相手に対して2万5千の兵を率いて出陣。
1584年の沖田畷の戦いで両軍は激突、兵力で勝る龍造寺軍が島津軍を押して始まりました。
少し足場が悪い畷(田んぼのあぜ道)でしたが、4倍もの兵力差ですから負けるわけがありません。ところが前線の動きが鈍くてなかなか進まない。
なぜなら、このとき前線では先鋒隊と2番隊が島津軍の鉄砲隊に挟撃されて壊滅寸前でした。敵将・島津家久は、劣勢のふりをして龍造寺兵を田んぼに誘いこんで袋叩きにしたのです。
そうとは知らず、こう着した様子にイライラした龍造寺隆信は前線に物見を行かせます。
龍造寺隆信に怒鳴られた物見の兵は、攻めあぐねる前線部隊に「命を惜しまず攻めろ」と余計な伝令をしてしまいます。将兵たちは無謀な突撃をして全滅しました。
一方、龍造寺隆信のところには島津兵が迫ります。てっきり物見が戻ったのだと思った龍造寺隆信は、不意をつかれて抵抗もできず、討たれてしまいます。
本陣の兵たちは逃げ出し、なんともあっけない最後となってしまいました。
生涯を簡単に振り返る
生まれと出自
1529年、龍造寺隆信は肥前国・水ヶ江城に龍造寺周家の長男として生まれます。幼いころは寺僧として過ごしますが、祖父と父が謀殺されたため、曽祖父に連れられて筑後国へ逃げます。祖父と父の仇を討った後、僧をやめて曽祖父を継ぎ、つづいて龍造寺宗家の家督を乗っ取りましたが、反対する家臣に追い出されました。
九州第三の勢力に急成長
その後、挙兵して水ヶ江城を奪い返すと勢いに乗り、主君筋にあたる少弐氏を滅ぼします。やがて大友宗麟との抗争に発展していきますが、大友氏が島津氏との戦いで大敗したので、大友派の国人を味方につけて北九州の一大勢力に成り上がりました。
最後と死因
従っていた有馬晴信が裏切ったので、やっつけるために出陣しますが、有馬軍に加勢した島津家久に沖田畷の戦いで敗れます。敵兵に囲まれた龍造寺隆信は大声で名乗ったのち、川上忠堅に討ち取られました。1584年5月4日、死因は討死。56歳でした。護衛の兵も逃げ出してしまったといいます。
領地と居城


筑後国を足がかりに、肥前国を本拠地とし、肥後国、筑前国、豊前国、さらには壱岐国、対馬国まで加えた五州二島が龍造寺隆信の領地でした。
龍造寺隆信の性格と人物像
龍造寺隆信は「頼もしいけどやっぱり怖いジャイアン」です。
熊の異名からもわかるように、勇猛果敢で冷酷無比、馬に乗れないほどの巨漢である様はまるでジャイアンです。
宣教師・ルイス=フロイスは「軍事的な決断はローマの将軍・カエサルをも凌ぐ即断」と評しており、ガキ大将としての素質にあふれています。
しかしながら、分別も久しくすればねまる(腐る)という持論があり、軽率に決断を急ぎてしまう反面も。
幼いころに命をねらわれたり、家臣に城を追われた経験から懐疑心が強く、疑心暗鬼になりやすいナイーブな一面があり、執念深く、裏切り者を決して許しません。
ずんぐりむっくりの肥満体、戦場では6人担ぎの駕籠に乗っていました。大酒飲みで、酒飲みを好み、酒が飲めない人を嫌います。隠居後は酒と女に浸り、それを注意する鍋島直茂を遠ざけました。
子どものころから体格に恵まれていて腕力が強く、頭も良かったので13歳のときには20歳くらいの知識がありました。寺僧だったころ、あまりの怪力で寺の門が外れてしまったことも。
実際に身に着けていたと伝わる甲冑『鉄錆地横矧二枚胴具足』が現存しています。
能力を表すとこんな感じ

即決できる決断力と行動力が龍造寺隆信の強みです。快活とは縁遠く、疑り深くて他人を信用しない性格が災いして、家臣からの信頼も得られません。
能力チャートは『信長の野望』シリーズに登場する龍造寺隆信の能力値を参考にしています。東大教授が戦国武将の能力を数値化した『戦国武将の解剖図鑑』もおすすめです。
龍造寺隆信の面白い逸話やエピソード
かーちゃんのキャラが強すぎる
龍造寺隆信の母・慶誾尼は、懐に短刀をしのばせ、いつでも死ぬ覚悟を持っていた肝っ玉かーちゃん。この親にして子あり。隆信の母も強烈なキャラでした。
/
家臣のところに
押しかけ婚
\
隆信の父で慶誾尼の夫・龍造寺周家は、少弐氏によって謀殺されてしまいます。内紛が相次ぐ家中で信頼できる者はなく、母子はピンチでした。
そんなおり、慶誾尼は妻を亡くしていた重臣・鍋島清房に「お前に新しい伴侶を見つけてやる」と告げます。
ある晩、なんのこっちゃわからない清房のもとに花嫁行列がやってきました。いよいよ困惑した清房が花嫁の顔をのぞくと、なんと花嫁は慶誾尼でした。

慶誾尼「清房、わしと結婚せえ」
清房には将来有望な息子がおり、その子がやがて我が子・隆信の助けになると考えた慶誾尼は、押しかけ婚でこれを息子にし、有力な一門衆としたのです。
このとき慶誾尼が義理の息子にしたのが、のちに龍造寺家の大黒柱となる鍋島直茂でした。
/
怯える兵たちに
奇襲を命じる
\
今山の戦いで、大友宗麟の大軍に村中城をすっかり包囲されてしまいます。
10倍の敵に囲まれ、隆信をはじめ龍造寺兵たちは絶望的になり、城内はお通夜のような雰囲気になりました。そこに慶誾尼が現れ、大きな声で叫びます。
慶誾尼「あんたたち、ネコに怯えるネズミかい!情けないったらないよ!」
つづけて慶誾尼は、鍋島直茂の指揮で敵陣に夜襲を仕掛けるよう命じ、あわてて出撃した兵たちは大友陣を急襲。大友軍を追い払うことに成功しました。
92歳で亡くなるまで、慶誾尼は龍造寺の母であり続けました。
討ち取られた首の返却を拒否されてしまう
沖田畷の戦いで島津家久に討ち取られた龍造寺隆信の首は、島津陣営で島津氏の当主・島津義久によって首実検が行われたのち、丁重に返却されました。
ところが、龍造寺陣営では「不運の首、受け取っても無益」と受け取りを拒否します。
拒否したのは、母・慶誾尼あるいは義弟・鍋島直茂とされますが、いずれにしても身内から拒否られてしまったのです。
前代未聞の塩対応をされて困った島津兵が首を持ってウロウロしていると、首は重さを増し、ついに岩ほどの重さになりました。
怖くなった島津兵は、近くの願行寺(熊本県)に首を埋葬します。一方で、首をとられた亡骸は龍造寺家によって龍泰寺(佐賀県)に埋葬されました。
首と胴体が離れ離れに埋葬された龍造寺隆信でしたが、明治になって鍋島家の菩提寺である高伝寺(佐賀県)に移され、280年以上を経てひとつの墓に入りました。
龍造寺隆信の有名な戦い
少弐氏を滅ぼした龍造寺隆信が、従おうとしない神代勝利に挑戦状を送りつけて起こった合戦。川上(佐賀県佐賀市大和町)で対陣した両軍は「千騎が一騎になる」と評されるほどの大乱戦を展開。反乱者によって神代周利が斬殺され、混乱した神代陣営は総崩れとなった。
川上峡合戦で龍造寺隆信は勝っています。
かねてから争ってきた少弐氏の家臣・神代勝利との決着をつけるため、堂々と正面から決闘を申し込む果し状を送りつけています。
急速に勢力を拡大する龍造寺隆信に対抗するため、大村氏と連合した有馬鎮純が東肥前を攻めた合戦。龍造寺氏は在地豪族の援護も受けて敵陣営を退ける。両軍は丹坂口(佐賀県小城市小城町栗原)で激突。千葉胤連の加勢を得た龍造寺軍が有馬勢を蹴散らし、潰走させた。
丹坂峠の戦いで龍造寺隆信は勝っています。
豪族たちを味方につける工作など、すでに戦略面で勝負を決めています。
肥前で勢いを増す龍造寺隆信を大友氏が攻めた合戦。大友軍は村中城(佐賀県佐賀市)を包囲するが攻めあぐねて4か月が経過。大友宗麟は弟・親貞に総攻撃を命じる。決戦前に酒宴をしていた大友陣営に鍋島信生が夜襲をかけて大友親貞を討ち取り、龍造寺軍が勝利した。
今山の戦いで龍造寺隆信は勝っています。
決戦を前に隆信は母・慶誾尼に一喝されてしまいます。母に気合を入れられて夜襲を決行し、見事に戦局を覆しました。勝利したのち、この戦いで敵対した近隣の豪族を討伐して、九州第三勢力にのし上がっていきます。
離反した有馬晴信を龍造寺隆信が攻めた合戦で、島津家久が有馬氏の援軍として参陣。泥田・沼地の沖田畷(長崎県島原市北門町)を決戦の地とした。地形を利用した伏兵戦術で、有馬軍と島津軍が圧勝。大敗を喫した龍造寺氏は、龍造寺隆信ほか多数が討ち死にした。
沖田畷の戦いで龍造寺隆信は敗れています。
龍造寺隆信のターニングポイントになった戦いです。
有馬晴信の裏切りを知った隆信は、怒り心頭して出陣します。圧倒的な兵力差に慢心していた感があり、軍略に長けた島津家久の術中にはまってしまいました。この敗北をきっかけに龍造寺氏は衰退していきます。
龍造寺隆信の詳しい年表と出来事
龍造寺隆信は西暦1529年〜1584年(享禄2年〜天正12年)まで生存しました。戦国時代中期から後期に活躍した武将です。
| 1529 | 1 | 龍造寺周家の嫡男として肥前国に生まれる。幼名:長法師丸 |
| 1536 | 8 | 宝琳寺の寺僧になる。 |
| 1545 | 17 | 祖父・家純と父・周家が少弐冬尚への謀反を疑われて馬場頼周に誅殺される。 曽祖父・家兼に伴って筑後国へ逃れ、蒲池鑑盛を頼る。 |
| 1546 | 18 | 曽祖父・家兼が挙兵し馬場頼周を討つ。 曽祖父・龍造寺家兼の死去により家督を相続。 還俗 → 龍造寺胤信 |
| 1547 | 19 | 少弐領・勢福寺城を攻める。 |
| 1548 | 20 | 龍造寺宗家の当主・龍造寺胤栄が死去。胤栄の未亡人と結婚し宗家の家督を相続。 大内義隆と同盟を結ぶ。 |
| 1550 | 22 | 改名 → 龍造寺隆胤 → 龍造寺隆信 |
| 1551 | 23 | 盟友・大内義隆が死亡。【大寧寺の変】 龍造寺鑑兼を擁立する土橋栄益らの叛乱により肥前国を追われる。筑後国へ逃れ、蒲池鑑盛を頼る。 |
| 1553 | 25 | 挙兵し龍造寺鑑兼から水ヶ江城を奪還。土橋栄益を捕らえて処刑する。龍造寺鑑兼を許す。 |
| 1556 | 28 | 少弐領・山内を攻める。神代勝利を追い出し三瀬城を奪う。 母・慶誾尼が鍋島清房と結婚。清房の子・信生(鍋島直茂)が義弟になる。 |
| 1558 | 30 | 神代勝利に三瀬城を奪い返される。 ”鉄布峠の戦い”*小河信安、石井兼清が神代勝利と交戦し討死する。 |
| 1559 | 31 | 少弐領・勢福寺城を攻める。少弐冬尚、千葉胤頼を自害させる。少弐家滅亡 江上氏が降伏、配下になる。 犬塚氏が降伏、配下になる。 |
| 1561 | 33 | ”川上峡合戦”神代勝利と決戦をする。敵陣で同士討ちが生じた混乱に乗じて大勝する。神代勝利は逃亡。 |
| 1562 | 34 | 神代勝利と和睦。 *鍋島信昌(信生=直茂)に平井領・須古城を攻めさせるが敗れる。 |
| 1563 | 35 | ”丹坂峠の戦い”有馬氏&大村氏が肥前国に侵攻してくる。千葉胤連と退ける。 少弐政興、馬場鑑周の少弐再興派が肥前国で挙兵。 |
| 1564 | 36 | 平井領・須古城を攻める。 少弐再興派の中野城を攻める。少弐政興、馬場鑑周を降伏させる。 |
| 1569 | 41 | 大友宗麟が肥前国に侵攻してくる。五箇山城、勢福寺城を大友氏に奪われる。 |
| 1570 | 42 | 大友宗麟が肥前国に侵攻してくる。 ”今山の戦い”大友宗麟が村中城に攻めてくる。今山の本陣を夜襲し大友親貞を討ち取り撃退する。 大友宗麟と和睦。 |
| 1572 | 44 | 肥前国に侵攻する。 |
| 1573 | 45 | 肥前国に侵攻する。 肥前国西部を制圧。 |
| 1574 | 46 | 平井領・須古城を攻める。平井経治を討伐し須古城を攻め落とす。 肥前国・須古城を居城にする。 |
| 1575 | 47 | 肥前国に侵攻する。 肥前国東部を制圧。 |
| 1576 | 48 | 肥前国に侵攻する。 |
| 1577 | 49 | 大村氏が降伏、配下になる。 |
| 1578 | 50 | 有馬領・松岡城を攻める。有馬鎮純(晴信)を降伏させる。 有馬鎮純が従属する。 肥前国を平定。 島津氏に大敗し大友氏が弱体化する。この機に乗じて大友領に介入する。 |
| 1579 | 51 | 筑前国、筑後国、豊前国、肥後国の国人衆を調略する。 |
| 1580 | 52 | 長男・龍造寺政家に家督を譲る。引き続き政治・軍事を主導する。 大友領・荒平城を攻める。 |
| 1581 | 53 | 鍋島直茂と共謀し島津義久と通じた蒲池鎮漣を猿楽の宴席に誘い出して謀殺、一族みな殺しにする。 *長男・龍造寺政家を総大将として肥後国に侵攻させる。赤星親隆、内空閑鎮房を降伏させる。 *龍造寺家晴を相良義陽の救援に向かわせ、島津忠平を退かせる。 |
| 1583 | 55 | *龍造寺家晴が島津忠平と高瀬川で対峙する。秋月種実の仲裁で和睦する。 |
| 1584 | 56 | 有馬晴信が龍造寺氏に叛く。 深江城を有馬晴信に攻められる。島津氏が有馬氏に加勢してくる。 ”沖田畷の戦い”有馬氏&島津氏に決戦を挑む。島津家久に敗れ討死。 |

- 龍造寺隆信 – Wikipedia
- 龍造寺隆信〜肥前の熊と呼ばれた男をわかりやすく解説|城写真の日本の旅侍
- 殿の首を受け取り拒否!? 戦国武将・龍造寺隆信の壮絶な最期…からの数奇な運命|和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!
- 慶誾尼 – Wikipedia
- 【九州三国志】慶誾尼――押しかけ女房の妙計!そして龍造寺家の未来を託した女傑(華盛頓) – エキスパート – Yahoo!ニュース
- 本郷和人監修『戦国武将の解剖図鑑』エクスナレッジ
- 矢部健太郎監修『超ビジュアル!戦国武将大事典』西東社
- 小和田哲男監修『ビジュアル 戦国1000人』世界文化社